こんにちは、ヤツPです!
薬局で働いていると、「医薬分業って当たり前じゃないの?」と思うことありますよね。でも実は、この仕組みが日本で広く定着するまでには150年以上かかっていて、しかも道のりはかなり波瀾万丈。ヨーロッパの王様の一言から始まり、戦争、国際的な圧力、政治と経済の駆け引きまで全部入り。今回はそんな“医薬分業ヒストリー”を、世界から日本まで時系列でたどりながら、「なぜ今の形になったのか」を一緒に見ていきましょう。
目次
世界における薬剤師の誕生
医師と薬剤師の役割を分ける考え方は、ヨーロッパが発祥です。
- 1200年ごろ
神聖ローマ帝国のフリードリヒ2世が「病気を診察したり死亡診断書を書く人(医師)」と「薬を厳格に管理する人(薬剤師)」を分ける制度を導入。 - 1240年
5か条の法律で、医師と薬剤師の人的・物理的分離、医師の薬局所有禁止などを明文化。
日本では明治時代にこの考えが入ってきます。当時は医師が処方も調剤も自分でやるのが普通でした。
日本における医薬分業の歴史
黎明期(明治〜昭和初期)
- 1872年(明治5年) 資生堂創業
化粧品大手として有名な資生堂、実は「日本初の西洋薬局」として銀座でスタート。創業者の福原有信(ふくはら ありのぶ)氏は薬剤師で、日本薬剤師会3代目会長も務めた人物。当時、西洋薬局は珍しく、かなり革新的な存在でした。 - 1874年(明治7年) 「医制」公布
日本初の近代医療制度。「医師たる者は自ら薬を売るな」と書かれるが、薬剤師不足のため医師が調剤できる例外規定あり。薬舗(ヤクホ)を開業するものは薬舗主(薬局の開業者)とされ、これが薬剤師の原型とされる。 - 1889年(明治22年) 「薬律」制定
薬舗は「薬局」、薬舗主は「薬剤師」として法的に定義。薬品の品質管理や広告規制も盛り込まれる。ただし医師による調剤も引き続き認められ、慣習は変わらず。 - 1906年(明治39年) 「医師法」「歯科医師法」制定
東洋医学と西洋医学が混在する中、医師・歯科医師の資格基準を国家で統一。 - 1918年 第一次世界大戦終戦
医薬品輸入が途絶し、国産薬確保が最優先に。医薬分業は完全に後回し。 - 1925年 「薬剤師法」改正
近代化と需要増に合わせ、薬剤師制度を整備。 - 1948年 「薬事法」「医師法」など制定(現行法の原型)
- 1950年 GHQによる分業勧告
公衆衛生福祉局長のサムス准将が「日本は薬漬け国家だ」と批判。先進国では当然の医薬分業が日本で全く進んでいないことに衝撃を受ける。
先進G7諸国は既に医薬分業が大きく進んでおり、日本の医師主導の調剤体制は驚きの対象だったようです。「医師が薬を売り」「歯科医師は金を売り」「薬剤師は雑貨を売る」とも揶揄されていました。
- 1951年 医薬分業法成立
調剤は薬剤師の独占業務としながら、「特別な理由があれば医師も調剤できる」という“但書”を盛り込み、事実上形骸化。 - 1956年 改正施行
任意分業のまま変わらず。ただし長野県上田地区では、国立病院が院外処方を出すようになり、地域薬局が一気に分業へシフト。
導入期(1974年〜)
- 1974年 診療報酬改定
処方箋料が6点(60円)から50点(500円)に大幅アップ。薬価差益も圧縮され、医師が院外処方に切り替えるインセンティブが急増。
ただし院内処方は情報共有や利益面で有利なため、大学病院などでは継続も多かった。
この年を、医薬分業元年とするケースが多いです。 - 1988年 病棟薬剤業務評価
薬剤師が病棟で患者の薬管理や処方提案を行うようになり、臨床チームの一員としての役割が広がる。これにより、病院内での薬剤師の地位が向上し、専門職としての責任と重要性が増しました。
成長期(1990年代〜)
- 1992年 薬価算定方式の変更
薬価差益(仕入れ価格と公定薬価の差)が減るように計算方法を変更。これまで医療機関にとって大きな収入源だった薬価差益が縮小し、経営面からも院外処方への切り替えがじわじわ増える。
時代背景:バブル崩壊直後で、日本経済は長期不況の入り口。医療費抑制が国の重要課題に。 - 1994年 在宅訪問薬剤管理指導料の新設
高齢化の波を見据えて、薬剤師が患者の自宅や施設を訪問し、服薬管理や残薬整理、副作用チェックを行う制度がスタート。薬剤師の活動の場が“病院・薬局”から“地域”へと拡大する大きなきっかけに。
時代背景:介護保険制度(2000年施行)に向けた在宅医療の基盤作りが進む。 - 1996年 服薬指導の義務化
薬剤師法改正で、調剤時の服薬説明が努力義務から法的義務へ。単に薬を渡すだけでなく、患者の理解度や安全性を考える“対人業務”が制度上も明確に位置づけられた。 - 2000年 お薬手帳制度導入
処方歴や副作用歴を一元管理するために全国導入。重複投薬や相互作用を防ぎ、複数医療機関を受診する患者の安全性を高める。 - 2003年 医薬分業率50%超
全国の処方箋の半分以上が院外で調剤されるようになり、分業がついに“当たり前”レベルに。 - 2006年 薬学部6年制スタート
医師・看護師と同じく、チーム医療の一員として臨床現場で活躍できる薬剤師養成を目的に教育年限を延長。長期実務実習も必修化され、薬剤師像が「調剤の人」から「薬物治療の専門家」へとシフト。 - 2006年 後発医薬品調剤体制加算の導入
ジェネリック医薬品の普及促進を目的に、後発品を一定割合以上調剤する薬局に加算を新設。 - 2008年 薬局が「医療提供施設」に明記
医療法改正で、それまで「医療関連施設」扱いだった薬局が正式に医療提供者として認定。薬局の社会的立場が制度的にも格上げ。 - 2009年 登録販売者制度新設
薬事法改正により、第2・第3類医薬品を薬剤師以外でも販売できるように。ドラッグストアやコンビニでの医薬品販売が広がる一方、薬剤師は専門性をより明確に示す必要性が増す。
成熟期(2015年〜)
- 2015年 「患者のための薬局ビジョン」公表
厚生労働省が「門前薬局から、かかりつけ薬局・地域連携薬局へ」という方向性を打ち出す。患者の服薬情報を一元的に管理し、在宅や地域医療にも積極的に関わることを求めるビジョン。
背景:高齢化と多剤服用(ポリファーマシー)の増加が社会的課題となり、薬剤師の対人業務強化が必須に。 - 2016年 かかりつけ薬剤師指導料の新設(調剤報酬改定)
特定の薬剤師が継続的に患者を担当し、24時間対応や医療機関との連携を行う仕組みが評価対象に。
狙い:患者と薬剤師の関係を“一見さん”から“伴走者”へシフトさせる。 - 2018年 地域支援体制加算の新設
在宅対応、地域連携、24時間対応、研修実施薬局など、地域包括ケアの中で薬局が担う役割を評価。調剤基本料の区分見直しにより、薬局間の機能差がより明確に。 - 2020年 グループ減算の適用強化
同一法人が近隣に複数薬局を構えている場合、調剤報酬の一部が減算される仕組みを強化。 - 2021年 新薬局認定制度スタート
薬機法改正で「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」の2つの新たな認定制度を創設。
地域連携薬局:医療機関・介護事業所などと連携し、在宅・退院支援を担う薬局
専門医療機関連携薬局:がんや難病など専門性の高い医療機関と連携する薬局 - 2021年 毎年薬価改定の導入
高額薬(例:2015年に登場したC型肝炎治療薬ソバルディ)の普及により医療費が急増。薬価を毎年見直すことで医療費抑制を狙う。 - 2022年 オンライン服薬指導・電子処方箋の運用開始
コロナ禍での非接触医療需要に対応し、オンラインでの服薬指導が本格解禁。
電子処方箋の導入で、処方データを全国レベルで共有可能に。 - 2023年 電子処方箋の全国展開
全国の医療機関と薬局が処方情報をリアルタイムで共有できるようになり、真の意味での“情報連携”時代へ。 - 2024年以降(予定)
調剤業務の自動化(調剤ロボット導入支援)
対物業務の効率化 → 対人業務評価へのシフト加速
在宅医療や健康相談機能を持つ薬局のさらなる推進
まとめ 歴史を知ることは、自分の役割を知ること
薬剤師として日々働いていると、目の前の処方や業務に追われがちですが、その仕組みがどうやって作られてきたのかを知る機会は意外と少ないものです。
医薬分業の歴史は、単なる制度変更の積み重ねではなく、戦争や国際的な圧力、経済政策、そして患者の安全を守るための数えきれない試行錯誤の連続でした。
150年という長い時間をかけて、薬剤師は「薬を渡す人」から「薬物療法の専門家」へと役割を進化させてきました。
この流れを知ると、自分が担っている仕事の背景や意味がより深く見えてきます。
歴史は過去の話ですが、そこには未来を選ぶためのヒントが詰まっています。
これからの薬剤師がどう患者や地域に向き合っていくか—それを考えるためにも、自分たちの歴史を知っておくことはきっと価値のあることだと思い記載してみました。
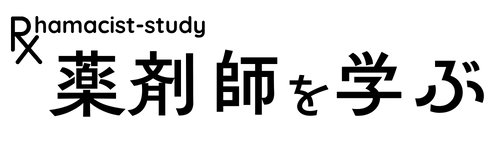

コメント