こんにちは、ヤツPです!
名刺交換をすると、つい肩書きに目がいってしまいませんか?
「部長」「CEO」「取締役」……なんだか英語で言い換えると余計にかっこいい。
そんな肩書きを見て、「この人とつながっておけば何か得があるかも」と感じたこと、一度や二度ではないはずです。
将来転職したい企業の人事かもしれないし、ビジネスの学びを得られそうな人物かもしれない。
あるいは、ただ何となく「凄そう」という雰囲気だけで、無意識に心酔してしまうこともあります。
 エド
エド肩書きってのはただの飾りだ。大事なのは、そいつが何をしてきたか、だろ?
でもちょっと待って。肩書きはあくまで“表面的な情報”に過ぎません。
今回は、肩書にある実態を見抜き、本質的に人を見極める視点を共有したいと思います。
肩書き一覧
一般的な肩書き一覧
まずは、日本企業でよく使われる肩書きの役割補足を表形式で整理しました。社会人になると当然みんな知っていることなのですが薬学生には馴染みがないと思いますので記載しておきます。
| 肩書き | 説明 |
|---|---|
| 会長 | 経営の最終責任者であり、社長の上位に位置づけられるケースが多い。 |
| 社長(代表取締役) | 組織の代表として意思決定の中心的存在。 |
| 副社長 | 社長を補佐し経営に深く関与する役職。 |
| 専務取締役 | 取締役の上位役職。 |
| 常務取締役 | 実務的な管理役職。 |
| 取締役 | 経営方針に関与する役員。 |
| 執行役員 | 従業員としての立場で最上位。 |
| 部長 | 部門の最高責任者。部門の方針や予算を統括。 |
| 次長 | 部長の補佐役。部門のサブ責任者。 |
| 課長 | 部門内に存在する一つの課のマネジメント責任者。 |
| 係長 | 課内でのリーダー的役割。 |
| 主任 | 一般職より一段上の職位。 |
| 一般社員 | 一般的な社員。 |
※上記は一例で、企業によって順番等が異なる場合があります。
薬局業界に当てはめると、
- 管理薬剤師:主任 (or 係長)
- エリアマネージャー/ブロック長:係長 (or 課長)
といった具合でしょうか。
なお、薬局業界では多くが中小企業となり、オーナー裁量が強く、「取締役」含め肩書きが名ばかりのケースがほとんどです。



名前や役職だけで判断せず、実態を見ることが大事なんだと思います。
肩書きの英語表現とその印象
最近は肩書きも英語表記が増えてきました。海外との取引きが増えてきたからと思いがちですが、たぶんほとんどはカッチョいいから英語にしている感じだと思います。特にスタートアップ界隈ではそんな気がします。
| 日本語 | 英語表現 |
|---|---|
| 代表取締役 | CEO (Chief Executive Officer) |
| 社長 | President |
| 専務取締役 | Executive Vice President |
| 常務取締役 | Senior Vice President |
| CFO | Chief Financial Officer |
| CMO | Chief Marketing Officer |
| COO | Chief Operating Officer |
| CTO | Chief Technology Officer |
| 部長 | (General) Manager |
| 課長 | (Section) Manager |
なお、英語表記を選択している企業でもC●O系以外の、実務レイヤーににおいては一般的な日本語の肩書きを使用するのがほとんどかと思います。
理由は、相手に??されるだけだから現場では困るという話ですね。
コンサル業界の肩書き一覧
コンサル業界では独自の肩書きが多く、特に外資系ファームでは以下のような階層構造が一般的です。
- Partner(パートナー):経営責任者クラス、案件獲得・経営責任を負う
- Director(ディレクター):複数案件の統括、および重要顧客担当
- Principal(プリンシパル):パートナー候補
- Manager(マネージャー):プロジェクトマネジメントの担当者
- Consultant(コンサルタント):分析・調査の主担当
- Associate(アソシエイト):若手メンバー、実行担当
- Analyst(アナリスト):新卒・ジュニアレベルの調査分析担当
ファームによって呼び名が異なったり、上記の職位がなかったりする場合がありますが、階層の目的は同じで、クライアントへの提供価値や責任範囲に応じて分類されています。
あとは”Senior(シニア)”をつけて、位を分ける場合もあります。例えば、Senior Consultant やSenior Managerなどですね。
ファーム
コンサルティングサービスを提供する企業そのものを指します。戦略系や総合系などに分かれ、例えば総合系だとデロイトトーマツ、PwC、KPMG、EYストラテジーのBIG4が有名です。



呼び名や形式だけでなく、責任の中身が重要です。
肩書きに惑わされない
それでは、本題の肩書に惑わされない思考術について考えていきます。
中小企業の肩書きは“盛られがち”?
「営業上の信頼」や「ステータス感」を得るために、実際の業務内容以上に立派な肩書きを使うことがあります。
たとえば、従業員数が数名の企業でも「取締役管理本部長」「執行役員マーケティング部長」などの肩書きを付けるケースは珍しくありません。
これは、信頼性やステータスを演出するためですが、実際には単なる飾りです。



かっこいい肩書きに踊らされるな。中身を見ろ。
つまり、名刺に書いてある肩書きだけを見て「この人はすごい」と判断するのは早計ということです。
あなたにとって“肩書き”は何を意味するのか?
肩書きには「ハロー効果」があります。つまり、一部の印象(肩書き)がその人全体の印象に大きな影響を与えてしまう心理効果のことです。
たとえば「CEO」と聞くと、「賢そう」「実績がある」「頼れそう」などポジティブなイメージを一気に抱いてしまいその人の全体像まで信頼しそうになります。
けれどそれは、裏を返せば“肩書きに踊らされる心理”でもあります。
名刺の肩書きを見たときに「この人、なんかすごそう」と感じるのは自然なことです。その背景には、
- この人とつながっておけば、転職の際にパイプ役になってくれるかもしれない
- ビジネスの勉強になるような話を聞かせてくれそう
- なんだかよくわからないけど、後々メリットがありそう
など、自分へのメリットを期待する心理が隠れており、肩書きは、ある種「可能性の象徴」として受け取ってしまうこともあるのです。
見るべきは“実質的な権限!”
肩書き以上に見るべきは「決裁権限」や「実行力」です。
大企業の課長よりも、中小企業やベンチャー企業の代表取締役の方が、自社の意思決定に関しては遥かに高い自由度を持っています。
つまり、名刺の肩書きよりも大切なのは、「この人がその場で決められるか?」という実質的な決裁権限なんです!



肩書きより何を決められる立場にあるのか。それを見抜く力が重要です。
上場企業の課長でも決裁権限数万円レベルだったり、よほどのことでない限りタクシー使わせてくれないケースがほとんどです。夢ない話ですが。
肩書きと実質的な権限を結びつけられるかが見るべきポイント
ビジネス上、一番確認したいのは決裁権限を持っているのかです。決済権限とは、業務上の意思決定や支出・契約などを最終的に承認する権限のことです。つまり、「あなたの判断でOKしていいよ」という会社から認められている範囲です。
なんでこんなに同じことを口を酸っぱくして言うのか。
「決裁権限」がない相手に時間をかけても、ビジネスの前進にはならないからです!
本人がダメでも、決裁権者につなげる力があれば意味がありますので、そこも踏まえて相手を見ていきましょう。
結局は、肩書きはあくまで判断基準で、目的は決裁権限を持つ人物にたどり着けるかとなります。



形式じゃない。本質を見る目が問われてんだよ!
決裁権限の有無を見極めることは難しい
ただ、なかなか確認するのも難しいのは確かです。
特に学生の方だとピンとこないですよね。
だからこそビジネス感度が問われる場所でもあるんです。
出来る人は
- 相手の企業規模や組織体制を把握する
- 相手のスキルや仕事の仕方(話し方や言葉遣いが丁寧か、専門的)かを観察する
- 容姿や身だしなみも参考に
といった内容を含めて少しずつ情報を集めて判断しますし、戦闘力の高いビジネスマンは瞬時に見抜きます。
だからこそ、実績を上げられ、高いお給料を受け取ることが出来るわけです。
つまり、肩書きに左右されるのではなく、相手がどんな権限が付与されているのかをしっかりと見極める癖をつけることが重要ということですね。
ちなみに、もしあなたが今の自分に肩書きを作るなら
名刺を渡す場面を想像してみてください。あなたが今の自分に肩書きをつけるとしたら、どんな表現にしますか?
| 日本語の肩書き | 英語表現 |
|---|---|
| 薬剤師 | Pharmacist |
| 管理薬剤師 | Chief Pharmacist |
| 学生(薬学部) | Pharmacy Student |
| 医療ライター | Medical Writer |
| 学術担当 | Medical Science Liaison |
どうしてそのような肩書きをつけようと思いましたか?
裏を返せば、相手もそういう心理で肩書きをつけているかもしれないですね。
ちなみにわたしはカッコいい肩書きにして、うぶな学生から『凄いですね!』と言葉をもらうのは嫌いじゃありません(笑)
終わりに
社会に出てから、特に名刺のやり取りが始まると、肩書きで相手を判断してしまいがちです。
私自身、若いころは確かに「部長」や「代表取締役」という言葉に気後れしていました。
かし、経験を重ねるにつれて、本当に見るべきは“その人が何を決められるか”という点であることが分かってきます。
ぜひ皆さんも、英語の肩書きやかっこいい言い換えの裏側にある人の心理や実態を冷静に捉えられる視点を持ってください。
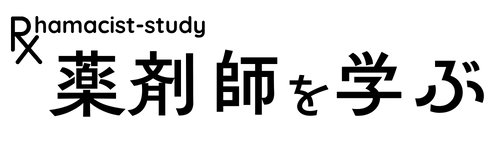

コメント