こんにちは、ヤツPです!
何となくで、就職先を選んでいませんか?
名前を聞いたことある≒大きな会社に違いない!とぼんやり考えていませんか?
「大きな会社って何?」と聞かれたらどう答えますか?
実は会社の規模の理解(正確には自分なりに捉えること)は、あなたがビジネスパーソンとなり年齢を重ねていく各ステージにおいて意味合いや重要性が異なってきます。
知らないより、知っている方がキャリアを自分で設計できる一つの要素になりますので、是非この記事を通して会社の規模について理解を深めてみてください。
今回は漫画「インベスターZ」の名言やキャラを交えながら説明したいと思います。
企業の規模は「中小企業」「中堅企業」「大企業」の3つに分けられる
会社の規模感を理解する上で、まずはこの3つの分類でOKです。
| 規模 | イメージ | 社員数(ざっくり) |
|---|---|---|
| 中小企業 | 地域密着、家族的経営も多い | 1〜300人 |
| 中堅企業 | 安定と挑戦の中間 | 300〜1,000人 |
| 大企業 | 誰もが知る超有名企業 | 1,000人以上 |
(※業界によって多少違いはあります)
 神代圭介
神代圭介「会社選びは“投資”だ。ブランドで飛びつく奴は、IR読まずに株を買うのと同じ。見るべきは規模でも知名度でもなく、事業の中身と伸びしろだ。
勝ちたいなら、数字と構造で選べ。」
と、本質はそうですが、構造という点では企業規模が大きく影響をしてきます。これは皆さまも感覚としても分かると思います。
規模による会社の違い
規模が異なるのは分かりましたが、実際にどのように違うのかを考えてみましょう。
まずは、組織構造と気になる出世争いですね。企業は外から中を、と中から中をみるのでは、その風景は全く異なります。例えば、シャトレーゼというお菓子専門店がありますが、非常に美味しいのに商品が安く提供されているためお客さんからは非常に好意的に捉えられています。でもその実態は、違法残業や下請けイジメ的なことでコスト削減を実現していたという笑えない実態もあるわけです。
と余談をしてしまいましたが、企業規模により組織構造は全く異なります。
組織構造と出世争い
| 規模 | 特徴 | 出世争い |
|---|---|---|
| 大企業 | 仕組み・制度が強固に完成 (イケてるドラマで見ていた企業の形) 各部門が機能している | 優秀な人材の中での競争が発生。年功・派閥・社内政治などに対応する様々な能力が問われる。競争者の質や母数とポジション数を踏まえてある程度の年齢でキャリアが見えてくる。 |
| 中堅企業 | 仕組みや制度が途上段階 オーナー含め個への依存大きい | 年功的な要素が強いが、役員層が高年齢化していれば、結果にあわせて時間的に数年レベルでの抜擢や昇給も期待できる。 |
| 中小企業 | オーナー(または代表者)の一存 | オーナーとの調整次第で、肩書は迅速に変化する。ただし、給与が大幅に上がることは期待が出来ない。オーナーとの距離が近いので良くも悪くも相性が重要。 |
簡単に記載してみましたが、大企業の強みは何と言っても組織構造がしっかりしており仕組化がされている点だと思いいます。逆に言えば、壊すのも大変で組織の硬直化という負の側面と隣合わせとなります。基本上司との相性は重要ですが、大企業は部署やポジションも複数あるので、最悪数年我慢すれば環境が変わり働きやすくなる可能性があります。
一方で、中堅企業と中小企業はぶっちゃけどちらも組織構造は結構適当です。それとどちらもオーナー(または代表者)の意向が隅々まで届きやすいので、オーナーがお金にシビアだったり権限移譲出来ないタイプだと活動もある程度制限される可能性があります。



「上に行くルートが決まってるか、ルールがないか。そこは大きく違う。」
裁量とスキル
ビジネスすると裁量権欲しいですよね。裁量と責任をもとにスキルが磨かれていく。それに教育制度が保管してさらなるスキル醸成を実現してくれるんだ!
はい。幻想です。サラリーマンである以上、何かしらの制限を受けながら仕事をするしかないです。でも規模によって異なる部分もあります。
| 規模 | 裁量とビジネススキル | 教育制度 |
|---|---|---|
| 大企業 | 若手のうちは限定的。業務が細分化されており、まずは一部の専門領域に集中。スキルは深く磨けるが、幅は出にくい。ただ、部門が多くローテーション出来る場合はゼネラリスト化も可能。 | 研修・eラーニング・ジョブローテーションなど体系的に整備。大手研修会社との連携もあり。ただし、形式的なものが多く実践的でないので、本人の意欲次第だがメリットは期待できない。 |
| 中堅企業 | 組織がフラットで、早い段階から一定の裁量を持てる。幅広い業務経験を積みやすく、ゼネラリスト志向に向く。 | 企業によってバラつきあり。OJT中心だが、成長企業では外部研修や自己啓発支援も行われている。(薬局業界ではほぼ無し) |
| 中小企業 | 人員が限られているため、新人でも企画や意思決定に関わるケースあり。スキルは「実戦型」で、本人次第だが経営的な視点も鍛えられる。 ただし、大きなビジネス機会は乏しい。 | 基本的にはOJT中心。制度としての研修は限定的だが、実務を通して学ぶ場面が多い。自発的な学習姿勢が重要。 |



「会社の制度に縛られるか、上司の機嫌に縛られるか、オーナーの思想に縛られるか。どこにいても、不自由なのは変わらない。
“自由に働けるか”は、環境じゃなくて、スキルの問題だ。
どこにいても通用する力を持ってる奴が、最後は勝つ。」
という形で企業規模によって運営スタイルは全く異なります。では、個々の視点から見た場合も参考ですが記載します。
企業規模と学生・ビジネスマンの視点
では、各ステージにおける企業規模への視点を考えてみましょう。
就職活動中(学生)の人の視点
自分が入る会社の「規模」を知ることはめちゃくちゃ重要!です。
- ビジネススキルや仕事の作法をしっかり学びたい、また安定志向の場合は「大企業」がおすすめ
- 裁量は欲しいけど、ある程度の組織基盤が欲しい人は「中堅企業」も選択肢に。
- オーナーの人柄やビジョンに共感できる場合や、将来の設計するよりまずは自分で考えて動きたい人は「中小企業」でもありです。
| 企業規模 | 特徴 | 考慮すべき |
|---|---|---|
| 大企業 | 制度が整っており、研修・福利厚生も充実。 ネームバリューもあり安心感がある。 | 年功序列傾向や社内競争が強く、成長スピードは遅め。ただし、売上による社会的ポジションは高く、M&Aなどで優位に成長も。 転勤ありのケースも。個の裁量は小さい。 |
| 中堅企業 | 裁量と安定性のバランスが取れており、成長産業に多い。業界内ポジションが明確な企業も多い。 | 組織の良し悪しが企業ごとに異なる。成長方向や経営陣の視野がカギ。 |
| 中小企業 | 裁量が大きく、スピード感がある。オーナー企業も多く、社長の考えが文化を決める。 | 事業の継続性や資金面に注意。マニュアルや制度が未整備なことも。 |
将来に必ず転職することを想定している場合や他業種に進むことを考えているなら「大企業」がおすすめです。
そして、このブログでも大企業をお勧めします。理由は1,000万を目指すには、転職やキャリアチェンジの際に確実にステップアップしていく必要があり、下記のようなメリットがあります。
ネームバリュー(経歴の説得力)がある
- 大企業での経験は、履歴書や職務経歴書の“看板”として知られている分強い。
- 特に異業種転職では「どんな環境で何をしていたか」が評価されやすく、「大企業出身」というだけで一定の信頼を得られる。
例として「トヨタ」「三井物産」「NTTデータ」出身、というだけで書類通過率が上がるケース多数。
基本的なビジネススキル・社会人マナーが叩き込まれる
- 社内研修、マナー教育、報告書の書き方、PDCAの回し方など、転職後も通用する「ビジネスの型」が自然と身につく。(薬局業界はそうでもないんですが。。)
- どの業種でも応用が効く「汎用スキル」が習得できる。
人的ネットワークが広がる
- 同期の数も多く、業界内外に転職する人が多いので、将来的に人脈資産として生きてくる。
- OB/OGが多いため紹介などで転職や副業に繋がることもある。
制度が整っており、キャリアを設計しやすい
- ジョブローテーションや社内公募制度で、社内転職のような経験が積める。
- 新規事業や出向などで、他業種的な経験が得られるケースも。
転職市場での評価が高い
- 採用側は「この人は大企業の選考を通過し、評価を得てきた」と判断しやすい。
- 面接でも「なぜ辞めたか」より、「なぜ大企業を経て次に進もうと思ったか」が問われる。
新卒サラリーマンの視点
もう就職した方においては、自社が業界でどの位置か?を理解するのが超重要です!
その上で、自分のキャリアアップに向けたアプローチを考えます。
| 自社の規模 | 特長 | 新卒が意識すべきこと |
|---|---|---|
| 大企業 | ブランド力、資金力、制度が圧倒的。だが、スピードは遅く保守的。 | 「強者の論理」に染まらず、自分の裁量と成長機会を意識的に探せ。 |
| 中堅企業 | スピード感と安定のバランス。現場主導の動き方が多い。 | 自分から「課題を見つけ、提案する力」が問われる。現場での突破力を磨こう。 |
| 中小企業 | 経営者や顧客との距離が近い。個人の影響力が大きい。 | 自社ブランドより「自分ブランド」を育てよ。武器を早めに見つけろ。 |



大企業に入って安心してしまった瞬間、成長は止まる。
「この会社で自分は何をすべきか?」
「業界の中で、この会社は何を戦っているのか?」
その“地図”を持たないまま働くのは、方向音痴のまま山に入るようなものだ。
中堅サラリーマンの視点
ある程度経験したサラリーマンの方においては、自社の規模というよりは、企業規模そのものを理解することで、自分のバリューの出し方が変わります。自社がどの規模なのか、相手(クライアント)がどの規模なのかを常に念頭に置いて仕事をすることが重要です。
| 項目 | 具体例 | 何故重要か |
| ① 取引先の“力量”が読める | 中堅企業相手の場合、担当者に言っても意味がない。社長に直接伝えないと。 | 相手の体質・スピード・決裁構造が読めると、営業や交渉の戦略が立てやすい |
| ② 転職市場での“自社評価”がわかる | 自社は売上100億あるけど、異業種では知名度は全くない | 転職で武器になるのは「ポジション×実績」で、それらは相手が想像し易ければし易いほどよい。 |
| ③ 転職戦略を描きやすい | 大企業→中堅企業管理職→中堅企業取締役へなど | キャリアアップには「どこにどんな経歴が刺さるか」の見極めながら絵を描くことが重要。 |
| ④ 競合や業界の“ポジショニング”が見える | 競合のM&A動向、自社の利点・弱点が見えるようになり、包括的に業界を理解するようになる。 | 事業戦略、提案内容、自分の成長領域に直結する“戦場の地図”になる。また経営視点をいかに身につけるかは競争力確保に重要。 |



「マーケットを知ることは、地図無しで冒険するのと同じだ。そんなことをするのは努力の無駄遣いでしかないね。」



「ビジネスで企業規模を知らずに働くのは、武器の射程距離を知らずに戦場に立っているとも言えますね。自分の会社が“どこで何と戦っているか”を把握すれば、使う戦術も、磨くスキルも、自ずと決まる。無知なまま動くやつほど、努力の方向を間違える。ということですね。」
まとめ|企業規模を知る=ビジネスの地図を持つこと
就活でも転職でも、「会社の規模感を見極める力」は、キャリアを左右する武器になります。
大企業・中堅企業・中小企業と、それぞれに魅力もリスクもあり、正解は人によって異なります。
大切なのは、「自分がどんな環境で力を発揮したいか」を見極めること。
その第一歩に、「企業規模の違いを知ること」だと思います。
見た目やブランドはモチベーションもあるので重要ではあるものの、
会社の中身、業界での立ち位置、そして“自分の価値がどう活きるか”を基準に、戦略的に選んでいきましょう。
1,000万円を実現するには、誰かがしてくれるのを待つのではなく、きちんと自分から階段を選択し登っていく必要があるわけです。
是非、企業規模という認識を覚えて素敵なキャリアを歩んでください。
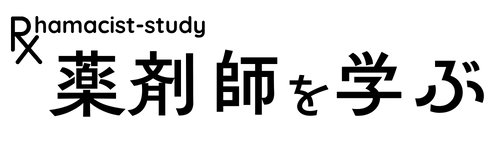

コメント